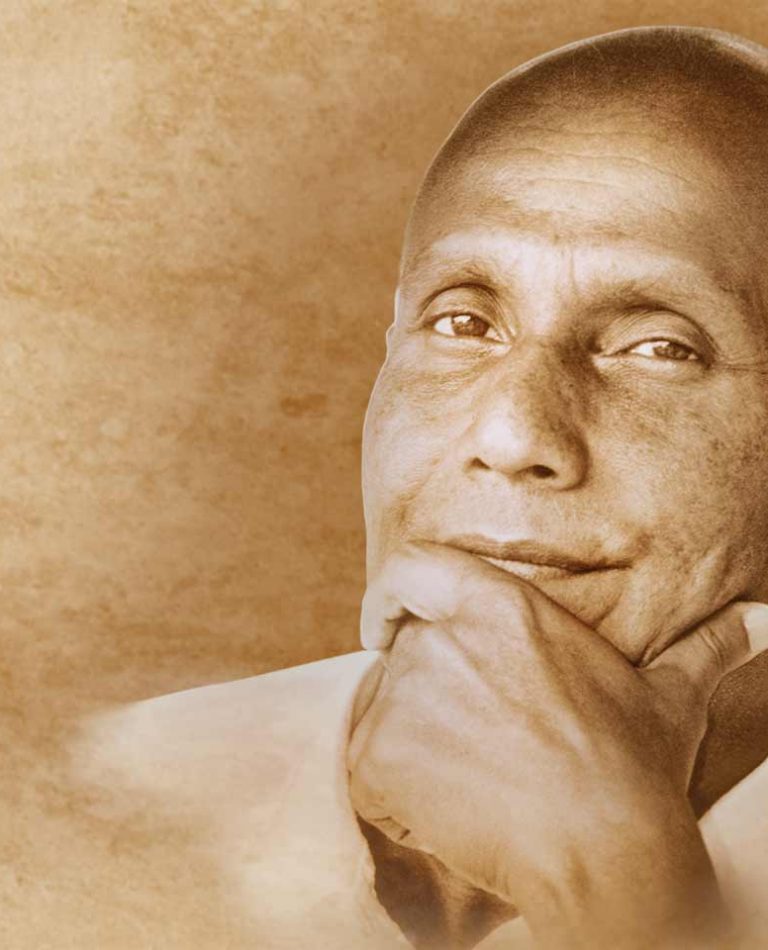シュリチンモイの略歴
シュリチンモイ(Sri Chinmoy) は1931年インドのベンガル地方に生まれ、1944年から1964年までの20年間を南インド、ポンディチェリーのスピリチュアル・コミュニティー(アシュラム)で過ごしました。長時間の瞑想修行を日々行う傍ら、勉学・スポーツにも精進し、詩などの文芸活動もこの時期に始めました。
1964年、内的啓示に従い、真実を探究する人々に西洋で奉仕すべく渡米。ニューヨークに居を構え、最初の2年間はインド大使館勤務の傍ら、その後は瞑想・平和活動に専心し、やがてアメリカ・ヨーロッパ・オセアニア・アジアに瞑想センターを開設しました。様々な国籍・文化・宗教の生徒に瞑想を教え、魂の師(スピリチュアル・マスター)として教え子の内的・外的な導き役となりました。
1970年、ウ・タント第三代国連事務総長の招きで、NY国連本部で国連大使や職員向けに平和瞑想を週二回行うようになり、2007年に他界する直前まで続けられました。この「国連での平和瞑想」【The Peace Meditation at the United Nations】は現在も志を継ぐメンバーによって継続されており、多くのプログラムや講演会、コンサートを定期的に開催しています。
シュリチンモイの瞑想哲学は、インドの古の智慧と現代のダイナミズムを融合したもので、深淵かつ非常に実用性があるものです。静かに座って瞑想するだけでなく、そこで得た内的平和などポジティブな資質を、外的活動で生かし、そうすることで自分を高め、世の中に真の意味で貢献できるのです。
シュリチンモイの深い瞑想から得た内的富は、詩などの文学作品・芸術・音楽・スポーツと多彩な方面で創造的に表現されていきました。自ら作詞作曲した曲を数十種類の楽器で演奏する形式のピース・コンサートは常に入場無料で、カーネギーホール、リンカーンセンター(以上ニューヨーク)、ロイヤル・アルバート・ホール(ロンドン)、シドニーオペラハウスなど、世界各地で700回余行われました。日本では、日本武道館(1992)他、鎌倉、京都、広島、大分、鹿児島などで行われています。
シュリチンモイの絵画はジャーナ・カラ(Jharna-Kala、泉の芸術)と呼ばれ、抽象画と鳥の絵の二種類が主なモチーフとなっており、平和の様々な側面を色彩と飛翔する鳥で表現しています。深い瞑想状態で描かれた作品は、大小数十万点に上り、国連本部事務局ロビー(ニューヨーク)、カルーゼル・デュ・ルーヴル(パリ)、インドネシアのバリ島デンパサール空港(常設)などで展示されてきました。日本でも2006年に鎌倉大仏殿高徳院で2週間、特別展示会を行いました。
シュリチンモイ・ワンネスホーム・ピースランは氏の平和とスポーツを愛する心から生まれました。平和の象徴「ピーストーチ」を掲げた多国籍ボランティア・ランナーが各国を訪れ、町から町へリレーしながら、学校訪問のほか、地元政府・地方自治体・市民グループなどと交流するもので、国籍や民族、文化を超えて皆が持つ平和への願いを共有するひと時を持ちます。1987年の開始以来これまで160カ国を訪れてきました。日本でも広島〜長崎、仙台〜秋田、北海道〜東京などのルートで計20数回行われています。
また、ゴルバチョフ元ソ連大統領の要請で同国の白血病の子供のために医療関連の人道支援を行なったことがきっかけとなり、人道支援サービス「涙も笑顔もひとつの心で」(Oneness-Heart-Tears and Smiles)が設立され、子供から子供へ真心の支援を橋渡しする「キッズ・トゥ・キッズ」(Kids to Kids)プログラムは災害等で困難な状況にある子供達を世界中で励ましてきました。日本では、東日本大震災の後、アメリカ・ロシア・チェコなどの子供たちからの「愛の絵」や手作りの小物などが届けられました。
国際シュリチンモイ・センターは国連グローバル・コミュニケーション局登録のNGO(非政府非営利組織)であり、氏の世界平和のための瞑想・芸術・スポーツ・人道支援活動は今も教え子や、志を同じくする多くの人たちの手で続けられています。
瞑想は喜びを与えてくれます。喜びは、実に大切なことです。人生で本当に喜びを大切にし、喜びの必要性を感じられたら、最善を尽くしてそれを得ようとするものです。そして魂から瞑想することでしょう。
ただ瞑想で上達したい、と思うだけでは長続きしません。瞑想を通して何が得られるのか知ってこそ、つまり瞑想からとてつもない喜びが得られるのだと知ってこそ、もっと上手くなろうと内的にも外的にも一生懸命励むようになるのです。シュリチンモイ
詳しくは以下のリンクもご覧下さい: